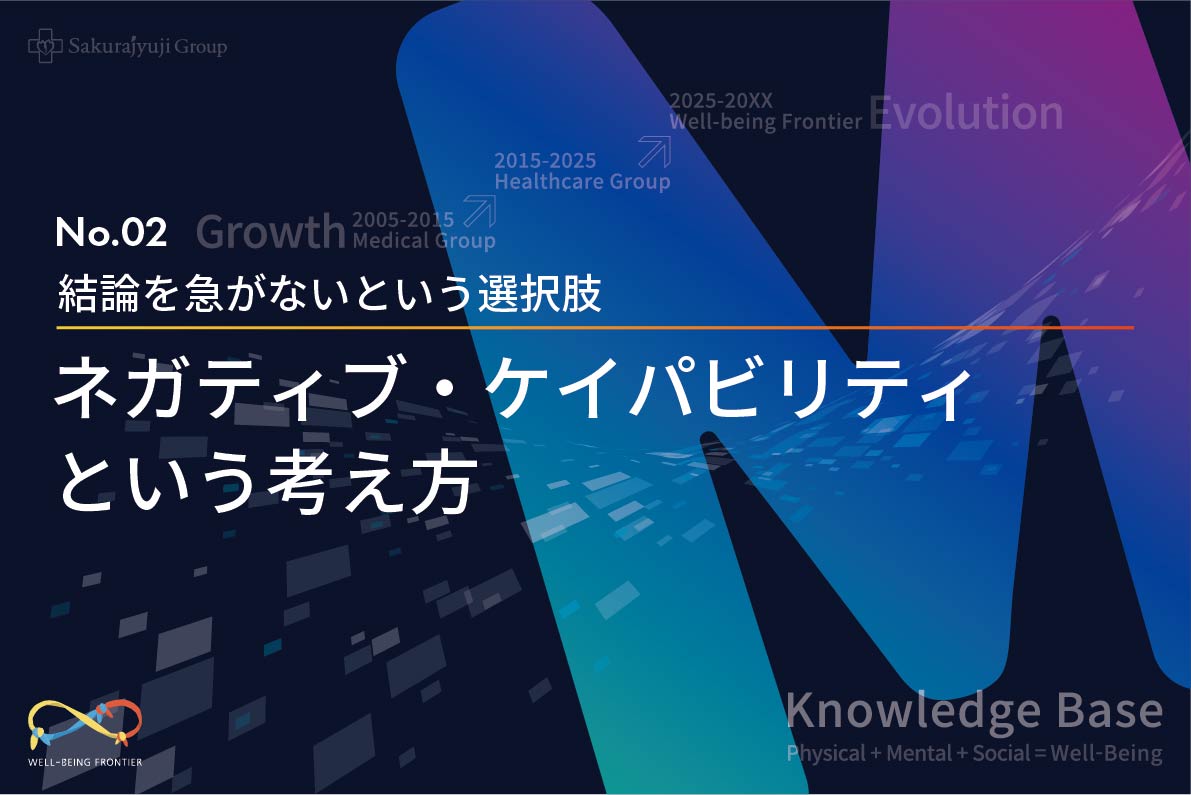私たちは日々、多くの情報と決断の中で生活しています。物ごとを素早く判断し行動に移す力は、今の社会を生きるうえで欠かせないスキルになっています。
しかしながら現実には、「どうするのが正解かわからない」「いまは結論を出せない」——そんな状況に直面することも少なくありません。たとえば、仕事での複雑な人間関係やケアの現場で相手の気持ちを想像しながら結論を出す場面などです。
そんなときに活きるのが、『ネガティブ・ケイパビリティ』と呼ばれる力(ちから)です。これは、どうにもならない状況やすぐに答えが出ない問題に対して、急いで答えを出さずにしばらくその状態を受けとめながら乗り越える力のこと。

2024年の国内研究では、ネガティブ・ケイパビリティの高い人は、感情の揺れが少なく、立ち直りも早い傾向があると示されました。また、それは“決断を先延ばしにする”のではなく、“今できることを探しながら待つ”という前向きな姿勢であることも明らかになっています(玉木・伊里・山田, 2024)。
さらに、2023年に発表された別の研究では、ネガティブ・ケイパビリティは「困難に直面したときに、気持ちを立て直しながら前に進む力」(=心の回復力:レジリエンス)に深く関係していることが指摘されています。とくに医療や介護、教育など、すぐに答えが出ない問題に向き合う現場では、「一度で解決しようとせず、状況を見守る余裕をもつ力」が、チーム全体の冷静さや協調を支える重要な要素になると考えられています(University of Geneva, 2023)。
医療の現場では明確な答えのない状況に向き合う場面が多くあります。ネガティブ・ケイパビリティは、そんな中でも判断を急がず、患者に誠実に寄り添い続ける力として注目されています。
「すぐに答えが出なくても大丈夫」。
そんな余白こそが、自分にも相手にも優しくあるためのひとつの在り方といえるのではないでしょうか。
確かな答えが見えなくても歩みを止めない力。それは、ケアをする人の心の安定や対話の質を支える力となり、精神的・社会的なウェルビーイングをかたち作るひとつの要素ともいえそうです。
参考文献
・ 玉木 賢太郎・伊里 綾子・山田 真希子(2024). ネガティブ・ケイパビリティ尺度の開発と妥当化. Jxiv(プレプリント).
・ Flandin, S., Scannell, O., Ketelaars, E., & Poizat, G. (2023). Negative Capability: A Human Factor of Resilience for Crisis Management and a Valuable Training and Intervention Objective. University of Geneva.